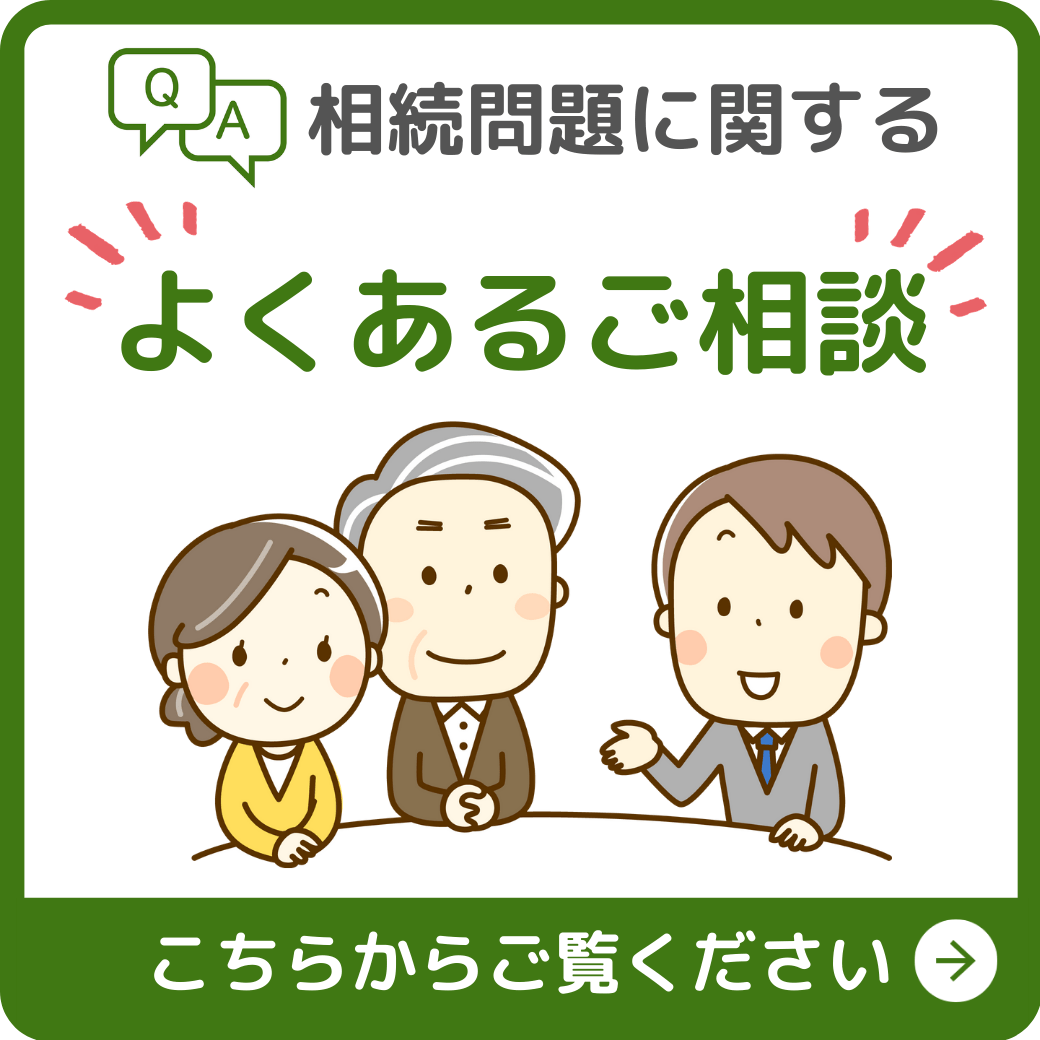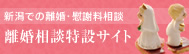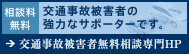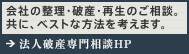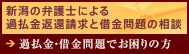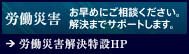はじめに
2018年に、民法の相続編が大きく改正されました。
このコモンズ通心でも相続法の改正内容についてご紹介しました(2019年3月号~5月号など※)ので、ご存じの方も多いと思います。
今回の連載では、相続法の改正内容について、以前の記事ではご紹介できなかった部分を中心に、概要を解説したいと思います。
_________
※このコラムは顧問先様向け冊子「コモンズ通心」にて掲載されたものです。
※過去の記事につきましては以下のとおりです。
・2019年3月号「配偶者居住権の新設」
・2019年4月号「仮払い制度等に関しての相続法の改正」
・2019年5月号「遺留分制度の見直し・特別の寄与の制度」
配偶者短期居住権の新設

例えば、長年の間、夫の持ち家にともに暮らしていた夫婦の場合を考えてみると、妻としては、夫に先立たれたとしても、それまで居住してきた家に住み続けたいと考えることが多いでしょう。
また、妻が高齢となっている場合には、新たな住居を見つけるということ自体が負担となります。
しかしながら、長年暮らした自宅不動産の所有名義が夫となっている場合、①夫が亡くなるとその自宅不動産は相続財産となりますから、子どもなど他の相続人と相続をめぐって争いになってしまった場合に、早期の立ち退きを求められることもあり得ます。
また、②遺贈などで自宅不動産が第三者の手にわたってしまった場合にも、直ちに立ち退けと言われる可能性が高いといえます。
このような場合には、少なくとも当面の間、配偶者(妻)の居住権を保護する必要があります。
この点について、判例(最判小判平成8年12月17日)は、被相続人と相続人との間で使用貸借契約(つまり、夫婦間での無償で住まわせるという内容の契約)が成立していたものと推認されるとして配偶者の保護を図っていました。
ただ、この判例法理によっても、上記②のような遺贈の場合などには居住権が保護されません。
そこで、今回の改正では、一定の要件を充たした場合には、一方の配偶者死亡後の生存配偶者が、居住建物を一定期間無償で使用することを法律の明文(民法1037条)で認め、保護することにしたのです。
短期居住権の内容
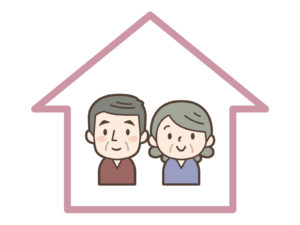
配偶者短期居住権には二つの類型があり、配偶者が居住建物について遺産分割の当事者となる場合(1037条1号。上記①のような場合)と、当事者とならない場合(同条2号。上記②のような場合)に分けられます。
細かな成立要件などは紙面の都合で割愛しますが、重要なのは居住権の存続期間です。
1号居住権の場合は、相続開始時から、遺産分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始のときから6か月を経過する日のいずれか遅い日までです。
2号居住権の場合は、遺贈等により居住建物を取得した者が、配偶者短期居住権の消滅を申し入れた日から6か月が経過する日までです。
つまり、1号と2号のいずれも、最低でも6か月は居住権が認められることになります。
なお、配偶者は、居住建物の通常の必要費(修繕費や固定資産税)は負担する必要があります。
<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2021年2月5日号(vol.253)>
※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。