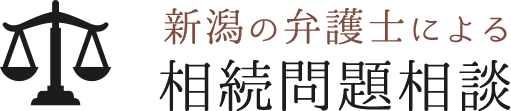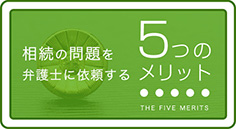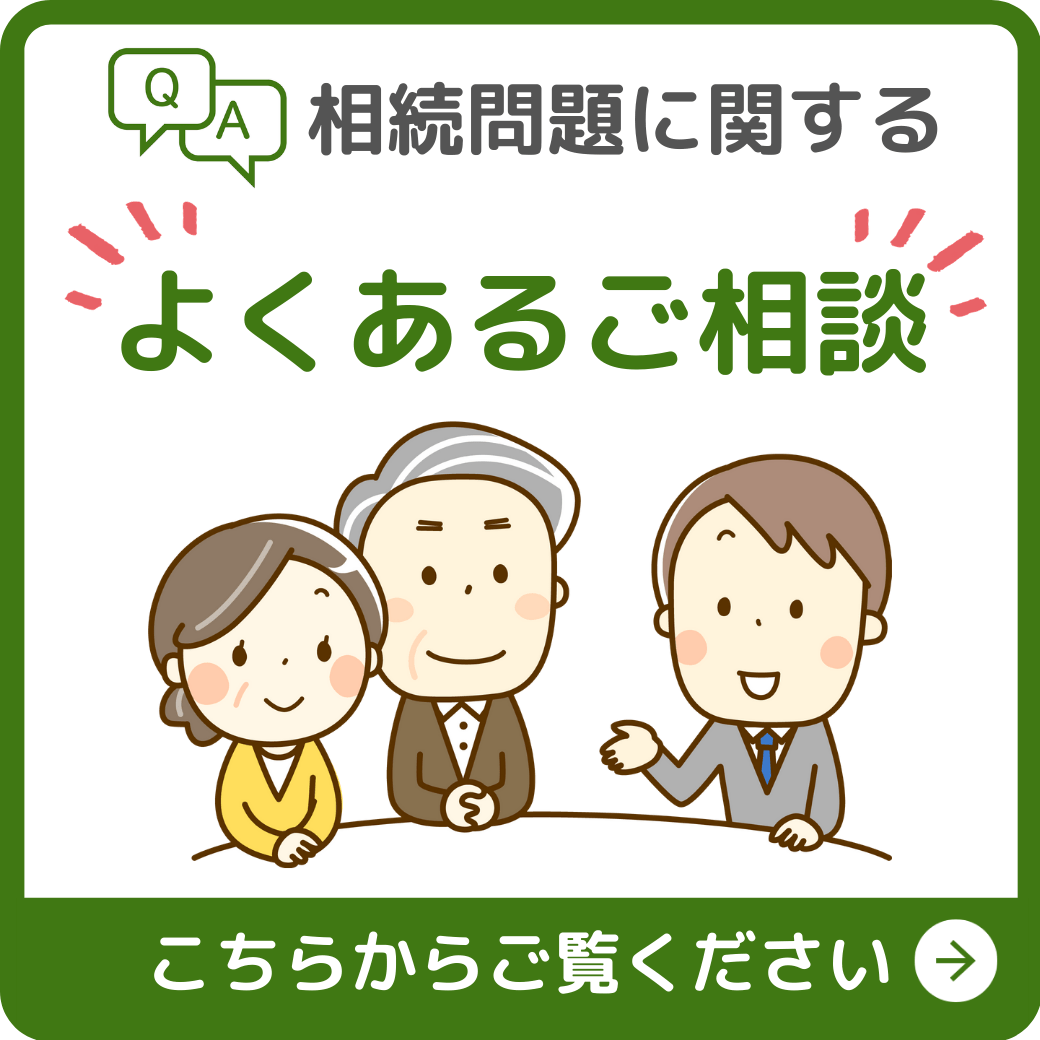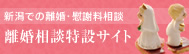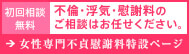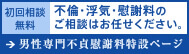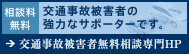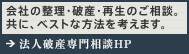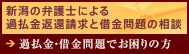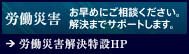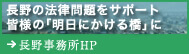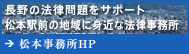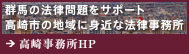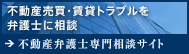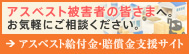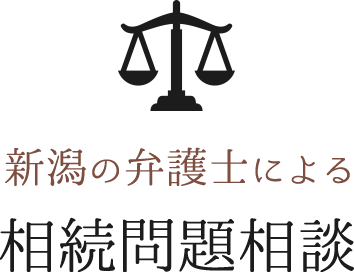相続が発生し、遺産分割について相続人同士で話し合おうとした際に、相続人の一人と音信不通であったり、事情により連絡が取れないといった事態に直面することがあります。
相続に関する手続きには期限があるものも含まれており、連絡の取れない相続人を除外して遺産分割協議を進めたいところですが、残念ながらそれはできません。
本記事では、相続人と連絡が取れない場合の具体的な対処法や、遺産分割協議を放置してしまうことの注意点を詳しく解説し、円滑な相続手続きを実現するためのポイントを取り上げます。
このコラムでわかること
・連絡の取れない相続人がいる場合の対処法
・一部の相続人と連絡が取れず、遺産分割協議を放置した場合の注意点
1.連絡が取れない相続人がいるとどうなる?
連絡の取れない相続人を除外して遺産分割や名義変更の手続きを行うことはなぜできないのでしょうか。
また、連絡が取れない相続人がいることで遺産分割協議を放置した場合、どのような問題やリスクにつながるのでしょうか。
相続のルールとリスクについて解説します。
遺産分割協議は全員参加が原則
遺産分割協議は、法定相続人全員の参加が不可欠になります。
法定相続人全員で協議を行い、合意した内容で遺産分割協議書に署名捺印することで、登記・金融機関などの対外的手続にも使用可能な効力ある文書とされます。
仮に、相続人が欠けた状態で合意しても、協議内容について後に「無効」と判断された場合、協議や手続きのやり直しをしなければならない可能性があります。
結果的に、時間や費用も余分にかかるだけでなく、相続人同士の信頼関係が損なわれるリスクも発生します。
また、連絡が取れない状況を放置すると、他の相続人にとっても財産の相続や処分、不動産の相続登記や相続税申告などの手続を期限内に完了できないなど様々なリスクが生じます。
そのため、早期に対策を講じ、どうしても連絡がつかない場合は法的手段を視野に入れることが重要になってきます。
【遺言書がある場合】
被相続人が遺言書を作成していて、遺産相続について相続分や財産の分配方法が明記されている場合、原則として遺言の内容が優先され、遺産分割協議は不要です。
ただし、遺言書に相続財産の一部についてしか明記されていない場合や、遺言書が法的に無効である場合など、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がある場合もあります。
無断で手続きを進めるリスクと無効の可能性
連絡が取れないからといって、その相続人を無視して手続きしてしまうのは非常に危険です。
協議の後にその相続人が現れた場合、既に進めた遺産分割協議の無効を主張されるおそれがあります。
さらに、相手への連絡や十分な説明を怠った結果、相続紛争が深刻化する事例も少なくありません。
状況がこじれてしまうと、調停や裁判などで解決しなければならない事態に発展することもあります。
◆遺産分割協議の関連コラム◆
相続人の一人が遺産分割協議に応じない場合~対処法からリスクまで徹底解説~
相続権はどこまで?法定相続人の範囲・相続順位を徹底解説
2.相続人と連絡が取れないケース別の対処法
相続人の行方不明や連絡拒否など、ケースによって対処方法は異なります。
それぞれの状況に合わせた最適な進め方を確認しておきましょう。
①相続人の住所がわからない
相続人同士が疎遠になっていて、従来の住所地に連絡しても応答がない、あるいは転居先が不明などの理由で居場所がわからないケースでは、行方不明者の戸籍謄本や住民票などを使って調査を進めることになります。
とくに戸籍の附票は住所の履歴が記載されているため、最新の住所を追える可能性があります。
それでも発見できない場合は、専門家の協力を得てさらに詳細な調査や家庭裁判所での手続きを検討することが必要です。
【戸籍の附票や住民票で住所を調べる】
まずは、相続人の戸籍謄本や戸籍の附票を取得し、最新の住所を追跡する方法があります。
戸籍の附票には、過去から現在までの住民票上の住所が記録されているため、引越し先の住所が記載されていることがあります。
戸籍附票は本籍地が分かれば、本籍地のある市町村役場に申請することで取得することができます。
現住所が判明したら、まずは手紙を書くなどして相手からの連絡を待ちましょう。
反応がない場合には、訪問するなどしてコンタクトを取っていきます。
住民票の取り寄せも有効ですが、第三者が請求する場合は正当な理由が求められるため、相続手続きなどの必要性を示す書類を用意することが大切です。
それでも所在がわからない場合は、弁護士など専門家に相談し、裁判所の手続きに進む検討も視野に入れましょう。
【家庭裁判所での不在者財産管理人選任申立】
住所を特定しても長期間連絡が取れず、かつ従来の住所に戻る見込みもないような場合には、法律上の「不在者」に該当する可能性があり、この場合は家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てることができます。
ご自身が法定相続人であればもちろんのこと、共同相続人でなくても、その不在者の財産に関して利害関係がある第三者であれば、家庭裁判所に対して不在者財産管理人の選任を申し立てることが可能です。
※ただし、実際には不在者と認定されるのはかなりハードルが高くなっています。
不在者財産管理人とは、財産に関わる手続きを進め、相続財産を管理する役目を担います。
家庭裁判所の許可を得て、相続人の代理人として遺産分割協議に参加することも可能です。
不在者財産管理人に選任されるのは、相続に利害関係を持たない被相続人の親族や、弁護士・司法書士などの専門家で、家庭裁判所が適任者を選任します。
共同相続人が不在者財産管理人になることはできません。
このような手段を活用すれば、相続人全員の権利を守りつつ、遺産分割協議を前に進められる可能性が高まるでしょう。
②連絡は取れるが応じてくれない
住所や電話番号など連絡先はわかっていても、相手方が話し合いに全く応じてくれないケースも少なくありません。
こうした場合でも、冷静に状況を伝え、相続手続き上の義務やリスクについて粘り強く説明し、場合によっては相続放棄を提案してみるなどの対応を行います。
それでも協力が得られない場合は、調停や審判など裁判所の制度を使うことが有力な選択肢となります。
【話し合いができない理由とその対処法】
連絡は取れても無視をされるなど、過去の兄弟間トラブルや感情的な対立が根底にある場合もあり、本人のみでは状況が進展しないこともしばしばです。
専門家や中立の第三者を介して話し合いを行うことで、感情的な衝突を緩和しつつ問題を整理することができます。
手紙やメールを活用して、感情を取り除いたやり取りをするのも有効な手段です。
相手の主張を正確に把握し、同時にこちらの意図や、相続上の問題点を相手に伝えやすくなります。
相続手続きを放っておくとどんなデメリットがあるかについて伝えることで、状況が進展することも期待できます。
それでも意見がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
調停でも話し合いが成立せずに調停不成立となった場合、最終的には遺産分割審判というかたちで裁判所に結論を委ねる方法を検討します。
審判となった場合には、審判で決まった内容に沿って「審判書」が作成され、その内容通りに相続手続きを行うことになります。
③生死不明の場合は失踪宣告を行う
相続人の一人が長期間行方不明であり、生死不明の状況が一定期間続いているとき、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てることができます。
失踪宣告とは、決められた期間消息不明な失踪者について、法律上死亡したものとみなす制度で、これにより相続手続を進めることが可能になります。
失踪宣告には、普通失踪と特別失踪の2種類があります。
①普通失踪…生死不明な状態が7年間続いている場合
②特別失踪…災害や戦争など 危難に遭遇した状況 において、 1年以上生死不明である場合
申し立てが認められると、家庭裁判所の審判によって「死亡したものとみなす日」が定められ、その日をもって相続が開始されたものと扱われます(民法第31条)。
通常は、最後の消息が確認された日から起算して7年を経過した日が死亡日とされます。
失踪宣告後は、残った相続人で遺産分割協議を進めることができます。
ただし、後に本人が生存していることが判明した場合、失踪宣告は取り消され(民法第32条)、財産の返還義務などが生じることがあります。
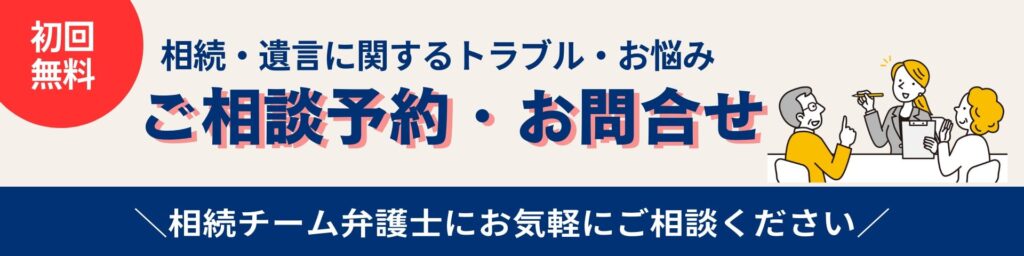
3.相続手続きが止まってしまうことで起きるリスク
連絡が取れない相続人の存在によって相続手続き全体が長期化してしまうと、さまざまなリスクが発生します。
主な問題点を見ておきましょう。
①不動産の売却・活用ができない
不動産や預貯金は相続人全員の合意による手続きが求められます。
特に不動産の名義変更には遺産分割協議書などが必要で、全員の実印や印鑑証明書などが揃わないと申請できません。
この手続きが進まないままでは、相続財産である不動産について売却や有効活用をしたくてもできず、結果的に不動産を放置して固定資産税などの負担だけが続くケースもあります。
また、2024年4月1日から相続した不動産についての登記(相続登記)が義務化され、正当な理由がないにもかかわらず期限(相続を知った日から3年以内)までに登記を済ませなければ、10万円以下の過料が科せられます。
相続登記の義務化はこちらのコラムで解説しています。
②預貯金の名義変更・使用ができない
金融機関の預金口座でも同様に、相続人全員の同意を示す書類が必要となります。
連絡の取れない相続人がいる限り、引き出しや名義変更ができないため、生活資金として使用することもできませんし、資産運用をして活用する機会も損失する状況が生じることもあるでしょう。
③相続税申告が期限に間に合わない可能性
相続税は原則として相続開始を知った翌日から10か月以内に申告と納税を行わなければならず、遅れれば加算税や延滞税が課せられる場合があります。
連絡が取れない相続人を待っているうちに、話し合いが進まず、この申告期限に間に合わなくなるリスクは大きいといえます。
最終的には法定相続分を元に準備申告を行う方法もありますが、正確な遺産分割協議がないままだと計算が困難であり、後から修正申告の手間が発生するため注意が必要です。
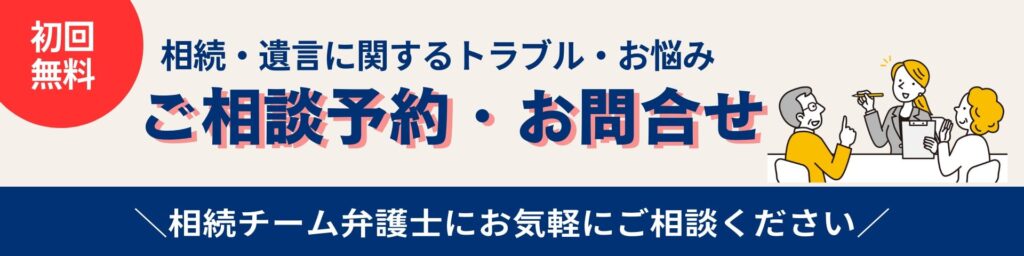
4.弁護士に相談するメリットと依頼できること
相続人の一人と連絡が取れない事態に陥ったときも、弁護士のサポートを受けることで手続きがスムーズに進む可能性があります。
相続問題を弁護士に依頼するメリットについてご紹介します。
弁護士ができること
弁護士であれば、戸籍・住民票の取得代理や、相続人調査に必要な調査嘱託の申請、戸籍・附票の職権取得も含めて、相続手続きに必要な業務を一括して請け負うことが可能です。
調停の申立てなど専門的な法律知識が必要となる局面でも安心感があります。
依頼者と他の相続人との間で交渉が難航している場合、第三者として間に入り交渉することで、感情面をうまくコントロールしながら話し合いを進め、穏便に解決するための橋渡し役となります。
不在者財産管理人を選任するための申し立てや失踪宣告に関わる書類作成など、専門性の高い業務にも対応可能です。
相続人調査だけでなく、相続手続きに必要な戸籍収集や財産調査など、相続全体に関してワンストップで対応いたします。
こうした対応を早期に依頼することで、後々の相続トラブルや手続きのミスを防ぐことができます。
5.早期対応と弁護士の活用が円滑な相続へ
連絡が取れない相続人がいると、遺産分割協議を円滑に進めることが難しく、相続税の申告や不動産の名義変更にも支障が出ます。
かといって、勝手に遺産分割協議を進めてしまうことはできず、勝手に進めた場合には、協議や手続きを一からやり直すことになりかねません。
そのようなリスクを回避するためにも、第一に相続人に関してきちんと調査・連絡を試み、必要に応じて家庭裁判所の手続きや不在者財産管理人の選任・失踪宣告などを検討する必要があります。
また、自力での対処が難しい場合には、早めに弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
相続手続きの必要書類は種類が多く、相続人が多い場合には揃えるだけでも労力と時間が必要となります。
またそれぞれの手続には期限がありますので、それと同時に相続人間で遺産分割協議を行っていくことは身体的・精神的な負担が大きくなりがちです。
早い段階から弁護士を活用することで、円滑な相続を目指しましょう。
当事務所では「相続・遺言」に関するお悩みは初回相談45分無料で承っております。
一新総合法律事務所の相続チーム弁護士に、どうぞお気軽にご相談ください。
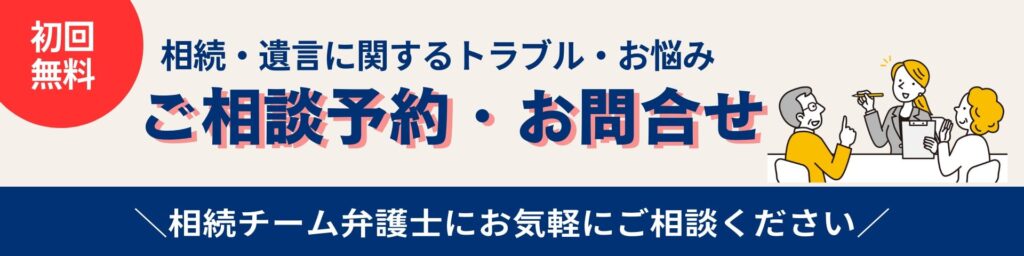
◆遺産分割協議の関連コラム◆
相続人の一人が遺産分割協議に応じない場合~対処法からリスクまで徹底解説~
相続権はどこまで?法定相続人の範囲・相続順位を徹底解説