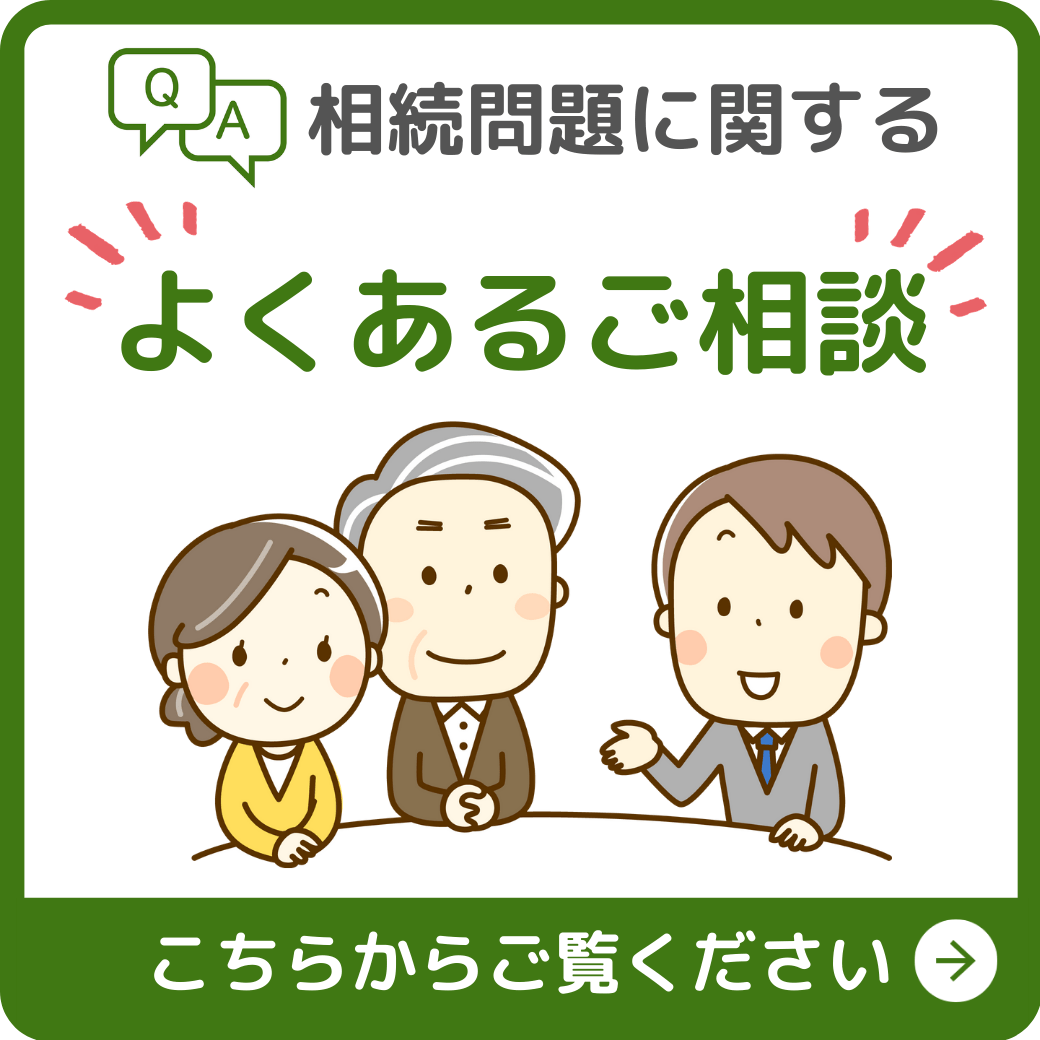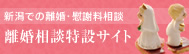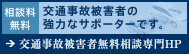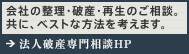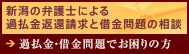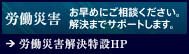1 はじめに
令和元年7月1日に施行された改正相続法によって、配偶者短期居住権の新設や自筆証書遺言の方式緩和など、相続分野の法制度が大きく変更されました。
そのなかで、遺留分制度についても根本的な見直しがなされたことはご存じでしょうか。
今回は、この「遺留分侵害額請求権」について概説したいと思います。
2 改正前の制度
そもそも遺留分とは、簡単にいうと、一定の相続人に保障されている最低限度の相続分のことです。
例えば、被相続人(亡くなった方)が遺した遺言によって、すべての遺産が相続人のうちの一人に渡ってしまい、自分は法定相続分すらも得ることができなかったという場合に、その一部を取り戻すことを認めたというのが、遺留分制度です。
実際に自分の遺留分が侵害されたときには、遺言等によって遺産を得た者(受遺者など)に対して請求を行うわけですが、改正前民法においては、この権利のことを「遺留分減殺請求権」と定めていました。「遺留分減殺請求権」は、その意思表示により一方的に法律効果を発生させる権利(形成権といいます)と解されており、その結果、遺留分を侵害するような内容の遺言等はその範囲で効力が消滅し、権利が当然に復帰するとされていました。
例えば、遺産が土地や建物等の不動産であった場合には、遺留分減殺請求の意思表示を行うと、当該不動産について遺留分割合の共有持分を得ることになります。
しかし、この共有持分というのが厄介であり、簡単に処分できないうえ、共有物分割請求といったさらなる手続まで必要になることもありました。

3 改正後の制度
そこで、改正法では、この遺留分減殺請求権を「遺留分侵害額請求権」とあらため、金銭で請求することが可能となりました。
つまり、遺留分侵害額請求の意思表示によって、遺留分侵害額に相当する金銭の給付を目的とする金銭債権が生じる(民法1046条1項)ことになったのです。
この改正により、不動産等について当然に共有状態が生じることを回避することができますし、被相続人の視点から
しても、「この不動産はこの人に渡したい」といった希望を尊重することができるのです。
反対に、受遺者(請求を受けた側)としては、金銭で支払う必要が生じるわけですが、場合によっては支払わなくてはならない金額が莫大となり、すぐに金銭を準備できない場合もあるでしょう。
その観点から、受遺者等は、裁判所に対して、金銭債務の全部または一部の支払いにつき、相当の期限の付与を求めることができるとされました(民法1047条5項)。
4 おわりに
今回紹介した遺留分制度に関する改正は、請求権の法的性質を根本的に変更するものですので、大きな改正といえると思います。
改正の是非については賛否両論あるようですが、例えば事業承継のために遺言で自社株式や自社工場、事業用資産等を後継者に引き継ぎたいという場合には、共有状態を回避できるので大きなメリットがあると思います。
この相続法改正では、上記のほかにも生前贈与の持ち戻し期間についての改正など、重要な変更がなされていますので、一度チェックされることをおすすめします。
<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2023年3月5日号(vol.278)>
※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。
相続・遺言・生前対策などのご相談は0120-15-4640までどうぞお気軽にお問い合わせください。
■「遺留分侵害額請求」に関する解決事例
・遺留分侵害請求権を行使した事例